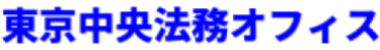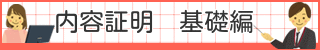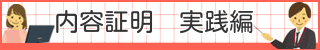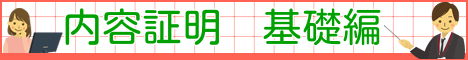
内容証明の次のステップ
内容証明を発送したあと、時効の援用やクーリングオフなど、到達によって完成するものは、その時点で完了しますが、貸金や慰謝料の請求、契約の解除、など、その後に相手方の行為が必要なものについては、相手方の対応によって、その後の取るべき手段を考えなければなりません。
・相手が受け取り回答してきた
・受取拒否
・不在・留置期間経過による返送
・受け取り後に無回答
など。
相手が受け取り回答してきた
相手が受け取り、回答をしてきた場合ですが、その内容で合意ないし示談をしても良いということであれば、改めて合意書や示談書などを作成して取り交わして解決することが出来ます。 相手の回答内容に合意が出来ない場合ですが、若干の条件面の調整で合意が可能なのであれば、改めて書面で再条件を提示してすり合わせを行い、合意ないし示談で勝解決が可能な場合もあります。 条件面での隔たりが大きく、応じられないということであれば、別途、自分で交渉するか、あるいは弁護士に依頼をして交渉をしてもらうか、もしくは、法的手続きを取るしかありません。
受取拒否
内容証明は郵便局の配達員による手渡しの「手紙」ですから、相手が受け取りを拒否することが出来ます。 この場合、内容証明郵便に 「相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否しました」と印字された用紙が貼られて差出人に返送されてきます。 相手が通知に記載した内容は把握していませんが、一切の交渉にも応じる気がないということになります。 そのため、訴訟や支払督促などの法的手続きをするしかありません。
不在・留置期間経過による返送
不在・留置期間経過の場合には、相手方が不在票に気付かないまま留置期間が経過した可能性もありますので、別途、特定記録(普通郵便の一種)で最終通告書とともに、発送済み内容証明のコピーを発送してみる、という方法もありますが、それでも無回答で応答が無い場合には、最終的には法的手続きを取るしかありません。
裁判所が取り扱う法的手続きには、民事事件、刑事事件、家事事件、少年事件、など、いくつかの種類があります。
このうち、内容証明を出した相手への訴訟申立や財産差押などの手続きは民事事件になります。
民事事件には、民事訴訟(通常訴訟、少額訴訟、手形小切手訴訟)、民事調停、支払督促、など、いくつかの種類があります。
民事事件の法的手続きには、色々な方法がありますが、以下に掲げる5種類が、主要なものです。
| (1) | 支払督促 |
| 金銭や有価証券などの一定の数量の給付を請求する場合の簡易な手続きで、出廷や立証が不要で、裁判官では無く、書記官による送達となり、そのまま強制執行まで進めることが出来ます。ただし、相手が行方不明の場合、「公示送達」を行なえませんので、それ以上の手続きが進められません。また、相手方から異議申し立てがなされた場合には、通常の訴訟に移行となり、実費の追加負担が必要となります。 | |
| (2) | 少額訴訟 |
| 金銭の支払いと目的としている事案で、請求する金額が60万円までの場合に、1回の審理で判決が出る簡易迅速な裁判手続きです。ただし、相手方が少額訴訟での審理を拒否した場合には、通常訴訟に移行となります。訴状の提出や出廷を必要とする点では、通常の訴訟と変わりありません。 | |
| (3) | 調停申立 |
| 生活の中で生じる身近なトラブルや事業の立て直し,親族間の問題などを抱えてお困りの方のために,裁判所の調停機関が,間に入って話し合いにより,適正・妥当な解決を図る制度です。裁判官と調停委員が関与することにより、法的妥当性や実情に即した解決の助言を受けながら進めることが出来ます。また、裁判と違って非公開のため、プライバシーは守られますし、期間も大半が3ヶ月以内に終了となるので、早期の解決が期待出来ます。ただし、あくまで「話し合いで合意を得る場」であり、強制は出来ませんので、当事者間の合意が得られない場合は、不成立となって終了します。 | |
| (4) | 通常訴訟 |
| 契約や損害賠償その他、法的な紛争の解決を図るため、公開の法廷で当事者双方が主張立証や反論反証を行い、最終的に裁判官が結論(判決)を出してくれる手続きです。正当な理由なく欠席すると、相手の主張を認めたものとして、不利な扱いを受けることが大半です。和解が付かない場合、第1審でも、6ヶ月~1年程度の長期間に及ぶことが大半です。 | |
| (5) | 仮差押え |
| 裁判の長期化により、相手の資産が費消や譲渡されて、充分な弁済を受けられくなる虞があるような場合に、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定のことをいいます。あくまで「口座の凍結」や「登記の禁止」などの処分を禁じる「仮」の命令になりますので、具体的に弁済を受けるためには、別途、通常の訴訟によって判決を取るなど、別途の法的手続きを行なう必要があります。 |
なお、財産差押えをするためには、給与差押えであれば給与を支給している勤務先の名称・所在地、口座預金であれば金融機関名・支店名、不動産であれば、その所在地や対象物件の登記事項、などが特定されていないといけません。 債務者の勤務先や預金口座、保有不動産、などが不明な場合には、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる「財産開示手続」というものがあります。 また、金融機関や法務局、市町村などの第三者から情報提供を得る「情報取得制度」という手続きもあります。 これらの詳細については、すべて、弁護士に、ご相談されて下さい。